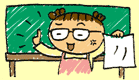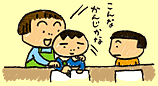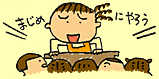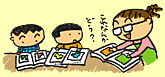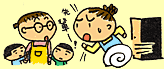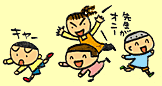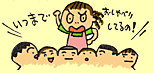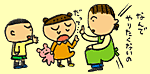|
● イライラをおさえ冷静を装って製作の説明を続ける
今日は製作をやる予定になっているし、作品展に間に合わなかったらたいへん。子どもの状態がどうであれ、とにかく製作の説明を始める。どうして話を聞けないのかしらとイライラするが、ひたすら笑顔で説明を続け、「さあ、やってみましょう」と材料を配って、先に進める。 |
|
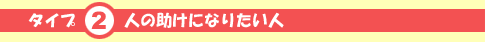 |
●やろうとしない子は、手をとってその気にさせる
「作品展まであと少しなんだから、がんばって作ろうよ」と道具を用意し、材料を配って、「こんな感じで、どう?」と、子どもたちといっしょに下がきを始める。手が動かない子には自ら手をそえて、「こんなふうにかけば?」と、やってもらおうと一生懸命になる。 |
|
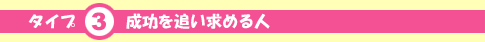 |
●まじめにやろうよと、子どもたちと話し合おうとする
「自分たちの作品展なのに、どうしてまじめに取り組まないの?」と、集中しない子どもたちを真剣に話し合う。「うまくできるとほめられるよ」と励まし、ひとりずつ、やる気を確認。全員の心をひとつにして作品展にのぞみたいし、その気のない子は、出品しなくていいとも思う。 |
|
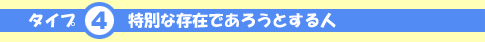 |
●ユニークな導入を考え、子どもたちと燃えたい
子どもたちのやる気をおもしろいやり方で刺激したいと、好きなものを探しに散歩に行く。石ころ、枝、葉っぱなど、みんなでいろいろなものを集め、「これで何かできるかな?」と、部屋に持ち帰る。子どもたちの目がいきいきとしてきたら、自分自身のやる気も高まってくる。 |
|
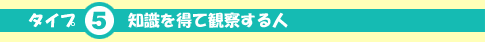 |
●落ち着かない子どもたちの様子を見ようとする
製作は導入が大事だと思うので、保育者向けの雑誌や美術書、今までの作品展の写真など、とにかく資料を多く集める。作品展に向けて。子どもたちの気持ちを盛り上げようと、自分でシュミレーションをくり返し、少し様子を見て、子どもたちが落ち着くのを待つ。 |
|
 |
●隣のクラスの先輩に相談してみる
自分では判断できないので、先輩に相談して決断を求める。アドバイスがあれば、とりあえず安心。今日やったほうがよいというアドバイスだったので、やる気のある子たちは製作にとりかかり、できない子は後日、個人対応で指導の時間をとることにする。 |
|
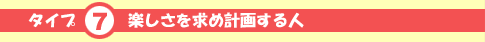 |
●思い切って方向転換し、体を動かしてあそんでしまう
何ごとも楽しくなければつまらない。製作は十分に動いたあと、時間があったらやってみようと思う。そのときの子どもの状態にもよるし、できるかどうかはわからないけれど、その気になれば、子どもたちはあっというまに作品を仕上げるから、そんなにあせることはないと思う。 |
|
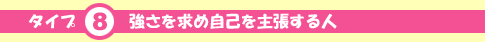 |
●「いつまでおしゃべりしているの!」と、一喝する
「さあ、製作の用意をしましょう。どのグループが遅いか、見ているわよ」と、目を光らせて子どもたちを観察。遅い子は名まえを呼んで注意し、早くしたくができた子は、気持ちをこめてほめる。全員のしたくがそろったら、「さあ、始めましょう」と製作の説明を始める。 |
|
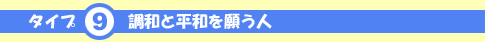 |
●子どもたちの気持ちを十分に聞いてみる
落ち着かない子どもたちと同じ目線になって話しかけ、子どもたちの今の気持ちを聞く。「やりたくなーい」「そう、そうして今はやりたくないの?」「だって外であそびたいもん」「じゃあ15分だけ外で遊んで製作をやろうね」と、条件を出して、子どもたちの要求をのむ。 |
|